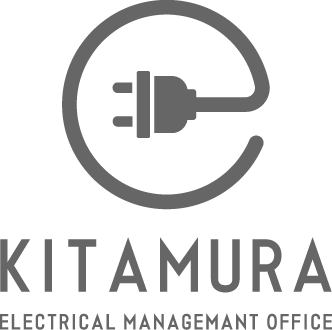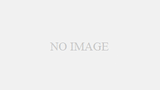本件の概要
感電事故を未然に防ぐために、注意点をまとめたリストをご用意しております。
以下のリンクからご利用ください。
報道発表資料
- 発表日:
- 令和7年6月30日(月)
- タイトル:
- 感電死亡事故の8割が危険箇所の“情報共有不足”に起因
~作業者が感電事故を防ぐポイントは?~ - 発表者名:
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構 国際評価技術本部
- 資料の概要:
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構[NITE(ナイト)、理事長:長谷川 史彦、本所:東京都渋谷区西原]は、作業者※1への危険箇所の情報共有が不足していたために起きる「自家用電気工作物に係る感電死亡事故(以下、感電死亡事故という。)」について注意喚起し、感電事故を防ぐポイントについてお知らせします。
NITEは電気工作物※2に関する事故情報データベース(詳報公表システム)を公表していますが、それを用いて、特に感電事故が多い需要設備等の感電死亡事故を分析しました。その結果、2022年度から2024年度までの間に、作業者の感電死亡事故は11件発生しており、うち少なくとも9件については、充電部等の危険箇所を作業者が把握できていなかった等の情報共有不足が主要因の1つであることが明らかになりました。さらに、二次請け以上※3の作業者の感電死亡事故については、7件中6件が情報共有不足によるものであることが分かりました。 -

 [図1] キュービクル(高圧受電設備) [図2] 受電室の感電死亡事故のイメージ※※実際の事故画像ではありません。
[図1] キュービクル(高圧受電設備) [図2] 受電室の感電死亡事故のイメージ※※実際の事故画像ではありません。電気主任技術者等の管理者※4や設置者、工事等の受注者は、作業者に危険情報が共有できていることを作業前に確認するようにしてください。さらに、作業者の安全が確保されるよう対策し、未然に感電死亡事故を防ぎましょう。
別紙1には、感電事故を防ぐために注意いただきたいポイントをまとめています。作業前の安全確認や、安全対策の見直し等にぜひご活用ください。
※1 電気関係の作業に従事している者、または電気工作物に近接する場所で行う作業に従事している者
※2 発電、蓄電、変電、送電、配電又は電気の使用のために設置する工作物のこと。例えばキュービクル(図1)
※3 設置者から電気工事等を受注した事業者(一次請け)から、業務の一部又は全部を依頼される事業者
※4 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者